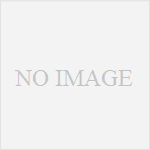1980年代に通産省は、ソフトウェア開発の需要増加に伴い、ソフトウェア技術者不足が深刻になると危機感をあおりました。ちょうど、電話が普及するときに、このまま電話が普及すれば電話交換手が足りなくなると言われたのと同じです。電話交換手は足りなくなるどころか、クロスバー交換機や電子交換機により交換業務は自動化され、ダイヤルインが認可されてからは、一般企業にはほとんどいなくなりました。
日本のコンピュータメーカーはソフトウェア開発をハードウェアの製造と同様に考え、ソフトウェア製造の工場化をめざしました。ソフトウェアの大量生産により、コストが下がると考えました。ソフトウェア技術者の採用を大幅に増やしました。その結果、ソフトウェア産業の各社は、ソフトウェア技術者の大量採用競争に突入しました。アルゴリズムやOSなどのコンピュータサイエンスを学んだ学生は大幅に不足し、その他の理科系の学生でも足りませんでした。文科系の学生さえ、「文科系でも論理的な思考能力さえあればプログラムは開発できます」と言って、ソフトウェア技術者として大量に採用しました。本当に論理的思考力に優れた学生が採用できればまだ良いですが、中小のソフトハウスでは、スキルが十分でない技術者を採用せざるを得なかったところも多いはずです。1980年代後半のバブルの時期には、理科系のトップクラスの学生は、ソフトウェア産業を嫌い、金融機関をめざしたのは皮肉なことです。
日本のコンピュータメーカーは、大量に受注したユーザーシステムの開発を、ソフトウェア子会社に発注しました。コンピュータメーカーのソフトウェア技術者は管理業務を行いプログラミングの現場からは遠ざかりました。ソフトウェア子会社は、地元のソフトハウスに発注し、やはり管理業務中心になりました。結局、コンピュータメーカーのソフトウェア技術者はプログラムを開発しなくなり、実力がどんどん低下していきました。実際にプログラムを製造するのは地元のソフトハウスだけになるという多階層の下請構造ができあがり、ITゼネコンと言われるようになりました。
このようにして、コンピュータサイエンスを学んだ学生は、コンピュータメーカーで管理業務に携わり、文科系の学生が中小のソフトハウスでプログラム開発に携わるといったパラドックスができあがってしましました。これが、日本のソフトウェア産業が発展しない理由のひとつです。