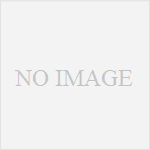ソニーの凋落は、1989年にコロンビア映画を買収したところから始まります。ハリウッドの事情に通じ、映画会社の経営に手腕を発揮できるとして選んだ経営者が、ソニーの資金を自分たちや家族の財布代わりに使い、なんら仕事らしい仕事をしなかったと表現されています。1995年に社長に就任した出井氏が、その責任を取らせるためソニー米国社長兼CEOを解任し、その後とった方針は、数字がすべてという米国式経営でした。
出井氏は「プロフェッショナル経営者」として、1999年より大規模な企業改革に着手しました。組織変更がしばしば行われ、新しい業績評価基準が導入されました。その結果、ソニーは売上至上主義に陥り、目先の利益だけを追い求めることになり、急速に官僚化していきました。
そして、経営者の権力闘争が始まりました。勝ち残ったのが、2005年に社長に就任したストリンガー氏です。彼は、創業者が中心となって立ち上げた小売関連事業を売却し、顧問制を廃止しました。「デジタル時代では製品の差異化は難しい」その結果「ハード(製品)では利益を確保することはできない」、それゆえネットワークビジネスの構築に価値を置き、家電製品はネットワークにつながるための「端末」にすぎないという方針で、エレクトロニクス事業からエンタテイメント事業への傾斜を強めました。リストラを進めましたが、ビジネスモデルがなく、どこで儲けるのか事業計画がはっきりしません。
ソニーのテレビは画質ではなく価格で勝負するようになり、市場の声に耳を傾けなくなったと書かれています。技術はコストカットの対象となり、大量の技術者が辞めていきました。優秀なエンジニアの流出は止まらず、技術のソニーに戻ることは、もう望めません。
帯には、「ブランドをダメにしたのは誰だ!」「ジョブズになぜ敗れたのか」と書かれていますが、技術者を冷遇した当然の結果に思えます。技術は人がすべてです。目先の利益を追い求めて技術者をないがしろにすれば、将来は望めません。著者は「数字がすべてという米国式経営」という表現をしていますが、米国式経営が技術を軽視するものでないことは、米国のハイテク企業を見れば明らかです。米国式経営を表面だけ真似た結果といえます。
技術を捨て、エンタテイメントに向かうソニーがどうなるか分かりませんが、業績悪化を契機に数字がすべてという経営に舵をきった結果、官僚化し、経営者の権力闘争がおこり、再生のための事業計画がはっきりしない会社は他にもありそうです。